安原顯編『私の好きな映画・ベスト5』(メタローグ、1994年)。かつての季刊書評誌『リテレール』の別冊。著名人へのアンケートを集約している。ときどきこうしたガイド本を図書館から借りてきて、これから見る映画の参考にする。この本の寄稿者は戦争を挟んで映画に親しんだ当時の中高年者が多く、欧米文学の研究者の割合が高い。そのため、少し古い外国映画が多く挙げられている。以下は抜粋(掲載順)。
安原顯編『私の好きな映画・ベスト5』(メタローグ、1994年)
安西水丸(イラストレーター)
- ミケランジェロ・アントニオーニ『情事』(1960年)
- フェデリコ・フェリーニ『甘い生活』(1960年)
- フランソワ・トリュフォー『突然炎のごとく』(1961年)
- ルキノ・ヴィスコンティ『若者のすべて』(1960年)
- テオ・アンゲロポリス『旅芸人の記録』(1960年)
中村とうよう(音楽評論家)
- スレイマン・シセ『ひかり』(1987年)
- グラウベール・ローシャ『アントニオ・ダス・モルテス』(1969年)
- テリー・ギリアム『未来世紀ブラジル』(1985年)
- セオ・アンゲロープロス『シテール島への船出』(1983年)
- 陳凱歌『黄色い大地』(1984年)
池田満寿夫(版画家、小説家)
- フェデリコ・フェリーニ『インテルビスタ』(1987年)、同『フェリーニのローマ』(1972年)
- ジム・ジャームッシュ『ストレンジャー・ザン・パラダイス』(1984年)
- ヴィム・ヴェンダース『パリ、テキサス』(1984年)
- フォルカー・シュレンドルフ『ブリキの太鼓』(1979年)
- ウディ・アレン『アニー・ホール』(1977年)
西澤潤一(工学)
- ルネ・クレール『巴里祭』(1933年)
- サム・ウッド『誰がために鐘は鳴る』(1943年)
- ヴィットリオ・デ・シーカ『自転車泥棒』(1948年)
- キャロル・リード『第三の男』(1949年)
- 黒澤明『生きる』(1952年)
丹生谷貴志(哲学)
- ヨリス・イヴェンス『風の物語』(1988年)
- ジョナス・メカス『時を数えて、砂漠に立つ』(1985年)
- マキノ雅弘『次郎長三国志』(1952年~)
- テオ・アンゲロポリス『シテール島への船出』(1983年)
- ジャン・リュック・ゴダール『軽蔑』(1963年)
粟津則雄がコメントに「ポール・ヴァレリーが映画について手きびしいことを言っている。映画とは、少量の絵画と少量の文学と少量の音楽と少量の演劇とをごたまぜにした代物であって、意識と注意力とのいっさいを動員するに値しないという趣旨であったと記憶する」と書いている。鋭いというか偏屈というか、いかにもヴァレリーらしい。
編集長の安原顯はこの本の後書きで「約300人の筆者に原稿依頼をしたところ」「89人しか原稿が集まらず」「たった3枚の原稿を書く暇もないほど多忙なのだろうか」「これが五流の後進国日本の実情」「日本のライター独特の甘え」とアンケートに応じなかった人たちに悪態をついている。しかし、安原自身、作家の生原稿の無断売却や寄稿者への原稿料の大量不払いが問題となった人だった。
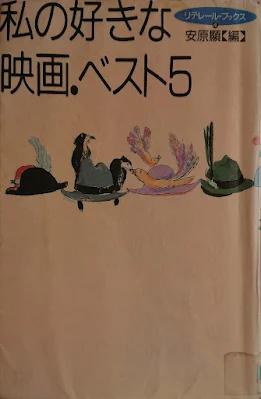
コメント